授業開始時にアンケートをとります。
提出必須ですので,必ずアンケートに答えなさい。
アンケートは2種あります。
アンケートはマークシート方式です。マークには鉛筆またはシャープペンシルを用いなさい。
1.京都大学 工学部授業アンケート
科目名:基礎情報処理演習(記載済を確認のこと)
アンケート時の注意「アナウンス」PDFファイル
2.地球工学科 授業評価アンケート
科目名:基礎情報処理演習T2,アンケート用コード:23010
アンケートの書き方「学生諸君へのお願い(地球工学科長)」PDFファイル
本演習時間の終了までに今までの提出レポートを受領しなさい。
受領しないレポートは、不要とみなし、担当教員で処分します。
創意工夫の見られるもの、丁寧に作ってあるもの、オリジナリティの感じられるものを高く評価します。
逆に、粗雑なもの、誠意の感じられないものは低く評価します。特に,他人の丸写しと断定できる場合は,写した者,写させた者両者の点数をゼロ点とします。(以前、断定されたことがあり、2人ともレポートゼロ点となり,当然単位もありませんでした。)
人には個性があるので、違う人が書いたプログラムが偶然一致する確率は極めて低いはずです。また、同じ理由でレポートが一致する確率も極めて低いはずです。相談するのは自由ですが、他人の丸写しは絶対にやめてください。
質問はメールで受け付けますが、質問に対する回答はヒントを与える程度のものと考えてください(できる だけ独力でやるようにして下さい)。また、回答には2日程度かかるものと心得てお
いて下さい。重要な内容を含む場合は、質問内容の回答をメーリングリストに流すことがあります。
最終課題は4題あります。
(課題1、課題2、課題3、
課題4)
難しく感じるかもしれませんが、どれも過去の課題や練習問題を踏まえてあるので、ここまできちんとやって来た人であればできるはずです。
課題の返却について:履修単位の確定後に返却します。特段の事情がなければ、後期のはじめの方と考えて下さい。詳細は掲示します。
![]()
最終演習時に指示するメールアドレス宛に演習の感想、中間・最終課題のおおよその所要時間と感想を書いて、送信しなさい。
「どの課題がどのような理由で面白かった(つまらなかった)」「この点をこうして欲しい」などを書いて下さい。
毎年、演習内容には前年度までの感想や要望を取り入れています。 ですから、今後の演習内容を改善する上で参考になるような意見を期待しています。
 課題2
課題2第1回から第12回までの演習で新たに自分で作成した(もしくはコンパイル等で自動作成された)ファイルを整理しなさい。また、最終課題で利用する(した)ファイルは、新たに一つのディレクトリを作成し(たとえば、last_report)、その中にまとめて整理・保存しなさい。
レポートは、最終課題のファイルが整理されているディレクトリィを含むいくつかのディレクトリィ内のファイルリスト(ファイル名と更新時間を含む)を提出しなさい。
 課題3
課題3以下の数式は、皆さんがすでに知っているもの、あるいは、今後触れる機会のあるであろうものです。これらをLaTeXで作成して出力しなさい。
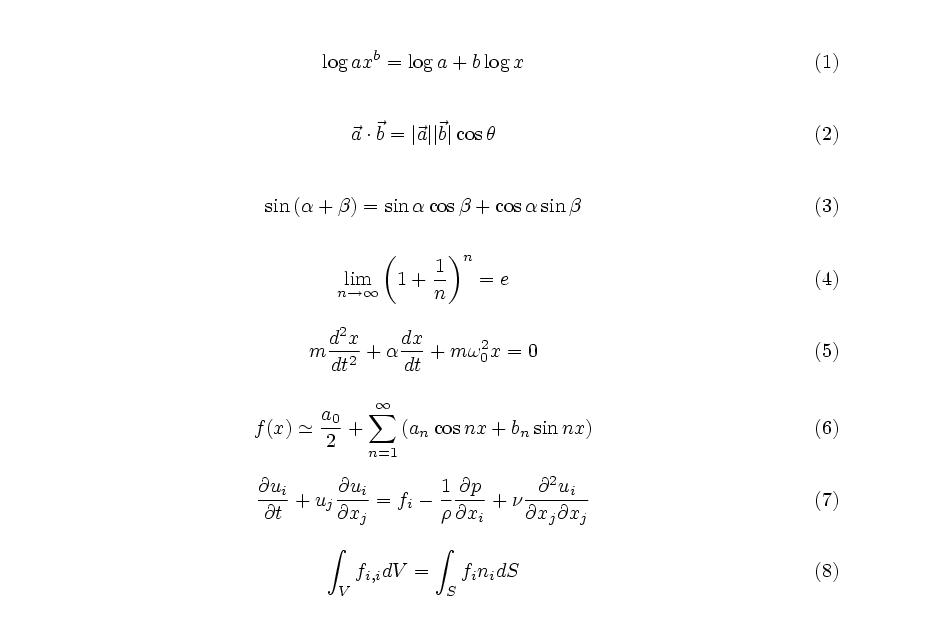
 課題4
課題4エネルギー消費量の増加が引き起こす問題の一つとして、大気中の二酸化炭素濃度の上昇による地球温暖化問題が挙げられる。そこで、今後の全世界におけるエネルギー消費量の増加について考えることにする。
世界のエネルギー消費を表1に示す15の国または地域に区分して考え、各区分において西暦2004年におけるエネルギー消費量を基準(初期値)とし、毎年一定の成長率でエネルギー消費量が増加(もしくは減少)するものと仮定する。
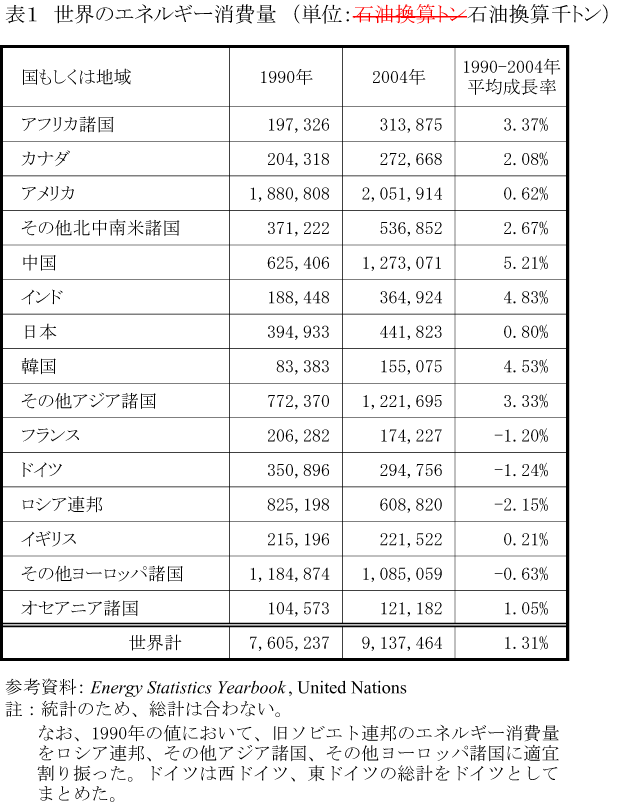
1.各区分におけるエネルギー消費量の成長率を入力すると、2005年から2050年各年における全世界のエネルギー消費量(15区分の総和)および2005年から2050年までの全世界累積エネルギー消費量(46年間の総和)を出力するプログラムを作成しなさい。
2.下記のケース(1)-(3)について、作成したプログラムを用いて2050年までの各年のエネルギー消費量を計算し、その結果を西暦を横軸にとった1つのグラフにまとめなさい。
(1)1990-2004年の全世界総計の平均成長率(1.31%)を15区分すべてに当てはめる場合。
(2)1990-2004年の各区分の平均成長率をそれぞれに当てはめる場合。
(3)アメリカ、カナダ、イギリス、日本などの先進国が負の成長率を示し(目安として2025年のエネルギー消費量が概ね1990年のエネルギー消費量になるようにすること)、その他がケース(2)の成長率を示す場合。
3.3つのケースそれぞれについて、以下の2つのシナリオにおける2005年-2050年までの二酸化炭素排出量の総計を求めなさい。なお、石油、石炭、天然ガスを1石油換算トン燃焼させたときに発生する二酸化炭素量は、炭素換算でそれぞれ0.78t、0.96t、0.60tであるとする。(プログラムを用いても用いなくてもよい。)
レポートは、ケース(3)の説明(参考にした「もの」がある場合は明記すること)および計算に用いた成長率の一覧表、3つのケースのエネルギー消費量の各年推移を示したグラフ、2050年までの累積エネルギー消費量、二酸化炭素の総排出量(表でまとめてもよい)、およびこれらの結果(内容)に対する考察および感想が必ず含まれるようにまとめること。作成したプログラム(ソースファイル)と実行例(1例でよい)は、最後にまとめて記載すること。
【考察にむけての補足】二酸化炭素21億炭素換算トンが、大気中の二酸化炭素濃度およそ1ppmvに相当する。
また、1880-1980年の100年間に大気中の二酸化炭素濃度はおよそ50ppmv上昇した(290ppmv→340ppmv)といわれ、世界平均気温は0.5度程度上昇したとされる。[註]大気温度上昇と二酸化炭素濃度上昇との関連については、まだ分かっていないことも多い。
(なお、出典は敢えて明記していません。興味のある人は、ウェブページ、学内の書籍検索などを用いて勉強してみて下さい。IPCC、地球温暖化、気象庁などのキーワードがよいでしょう。)
![]() もちろん演習時に講述しなかった命令文を使ってもかまいません。(その時は、自分でその用法をよく理解しておくこと。)
もちろん演習時に講述しなかった命令文を使ってもかまいません。(その時は、自分でその用法をよく理解しておくこと。)
 戻る
戻る